海水は比較的電気を通しやすい性質を持つため、地磁気の中を海水が流れるとダイナモ発電が起こり、電場と磁場が生じる(図1)。海岸近くや海中で地磁気や地電流を観測すると、このような海流起源の電磁場変動をとらえることができる。
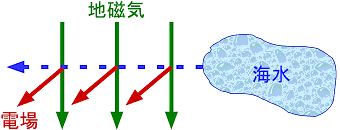
海洋起源の電磁場は、海水の流量を手軽に知る手段として今後の利用が期待される一方で、火山島での火山活動監視用の電磁気観測にとってはノイズという面も持っている。例えば、三宅島や伊豆大島の海岸近くの観測点では、黒潮が島に近づいたり遠ざかったりするたびに大きな磁場変動が観測され、火山性の磁場変化をしのぐこともしばしばである。地下深くにマグマがある場合は火山性磁場変動の振幅も小さいので、噴火の準備過程など前兆的な変動を監視するためには、海洋起源の電磁場変動を正しく見積もる手段を持っておく必要がある。
気象庁は海洋総合解析システムを用いて、黒潮を中心とする日本近海の海流の数値モデルを作成している。本研究では、この海流モデルを利用して、海洋起源の電磁場変動を定量的に見積もることを試みた。
まず、三宅島の全磁力と、海洋総合解析システムの流速の相関を統計的に調べた。流速3成分は、深さ方向に7層、水平方向に約12km間隔の格子状に分布している。このうち、三宅島周辺の300〜500格子点を選び、比較的変動の振幅が大きい浅い層での水平流速を中心に計算に利用した。全磁力は、三宅島の5観測点で2001年3月から2002年6月に観測されたデータの中から超高層起源と地球中心核起源の変化を除去し、局所的なトレンドを抽出したものを使用した。全磁力トレンドと水平流速とで主成分分析を行ったところ、格子点範囲や層に関わらず、全磁力トレンドと水平流速の間には高い相関が見られることがわかった。しかし、相関する成分の時空間パターンは時空間範囲や層によって一定せず、定量的関係を同定するには至らなかった。

主成分分析を通じて海流モデルに海洋ダイナモ現象に対する十分な解像度があることが示唆されたので、次に、水平流速を入力に用いて誘導電磁場を数値的に計算した。長周期変化だけに注目し、海を含む地表面10kmにだけ電流が流れるモデル空間を用いることで、薄層近似を適用できるように問題を極めて単純化し、海表面から海底面までの平均水平流が誘導する電磁場を有限要素法によって計算した(図2)。計算領域は、2000〜3000km四方で、12km x 12kmの等方格子を組んだ。地磁気分布はIGRFモデルを利用し、海水の平均電気伝導度は海洋総合解析システム海流モデルの塩分濃度・温度・圧力の値から標準海水モデル式を利用して換算した。海の深さはETOPO5モデル、堆積層の厚さはハーバード大学のモデルを利用し、電気伝導度として堆積物に0.1S/m、それ以外の岩石に0.01S/mを一律に与えた。
これらの計算から、海流による長期的な変動の大雑把な傾向は把握できることがわかった。境界付近の流れによる計算値の振動が見られるなどの精度上の問題があるので、境界条件および計算ルーチンの高度化に取り組んでいる。
