本研究は、気象庁で運用されている雷監視システム(LIDEN)の支援に向けて、雷雲通過時に大気電場観測において観測される、大気電場の急変現象を調査し、その変動特性等の基礎資料の充実を目的とした研究である。
昨年度までの調査で、雷雲接近時の大気電場の急激な変化は、大気電場観測点から雷雲に対応する降水レーダーエコーまでの距離に良い相関がある事が分かった(図1)。しかし、雷を伴わないレーダーエコーの接近時にも、雷雲が接近してきた時と同様の大気電場の変動を観測した事例があり、大気電場は、すでに発雷している雷雲だけでなく、発雷するまでには至っていないがある程度発達した積雲にも反応しているという事が予測された。今年度は、調査対象を2006年度に地磁気観測所の大気電場観測装置(水滴集電器)で、発雷の有無にかかわらず±500V/m以上の急激な変化を観測した事例として、LIDENデータ及び降水レーダーデータとの比較を行なった。
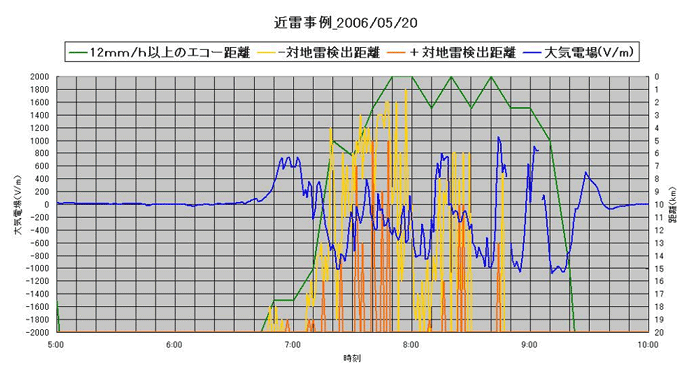
2006年度に大気電場の急変が観測された事例は、計57事例あった。各事例日の-10℃の気温高度エコー強度を比較すると、1事例を除き、雷電の有無に関わらず柿岡から半径30km以内に20dBz以上の反射強度を持つエコー領域が存在することが分った。-10℃の気温高度の強エコー領域では対流雲中で雹(ひょう)や霰(あられ)が作られ、この雹や霰の摩擦による電荷分離が大気電場の急変の原因と考えられる。(図2)
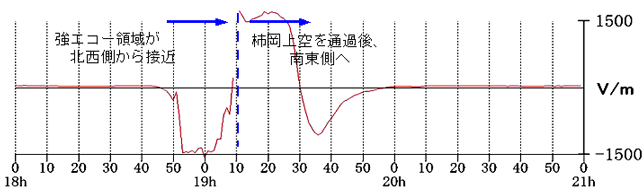
急変事例とLIDENによる雷検知データとを比較すると、地磁気観測所を中心とした半径50km以内でLIDENが雷を検知していた事例は34事例あり、全体の60%程度であった。雷を伴わない場合の23事例に着目すると、寒候期*(10月から4月)に18事例と集中していた。5-9月の暖候期*と10-4月の寒候期*の大気電場急変事例の最大変化幅の平均を取ると、暖候期は約±800V/mであったのに対し、寒候期は約±1100V/mと大きいことが分った。
暖候期と寒候期の-10℃の気温高度を見ると、暖候期は5〜7kmであったのに対し、寒候期は2〜5kmと低く、大気電場急変の原因と考えられる-10℃高度のエコー領域の高低が大気電場の変動幅の違いとなっていると考えられる。
今年度の調査で、対流雲の通過時に発生する大気電場の急変現象は、-10℃高度のレーダーエコーの強度や高低及び水平距離により説明できる可能性を見出した。今後は更に詳細な解析を続け、大気電場での雷検知及び雷予知に向けた基礎資料としたい。
(*) 気象用語としては、寒侯期は10月から3月、暖侯期は4月から9月になります。
