研究代表者:山﨑伸行
東北地方太平洋沖地震の発生時に、「いわき」観測点において、全磁力値が減少する異常な地磁気変動が見られました(図1)。
東北地方太平洋沖地震は、マグニチュード9.0の超巨大地震です。このことから、地磁気の異常が、「いわき」観測点だけでなく、より広い範囲に及んでいる可能性があります。そこで、「いわき」観測点の他に、女満別・柿岡・北浦(地磁気観測所)、江刺・原町・鹿野山(国土地理院)、八ヶ岳(東京大学)のデータも調査しました(図2) 。ただし、広域の地磁気の値を比較する場合、上空起源のノイズの影響が大きくなります。このノイズの除去について、カルマンフィルターを用いて解析処理を行いました。カルマンフィルターの参照点として、震央から1200㎞離れた父島の毎分値を用いました。図2を見ると、東北地方太平洋沖地震に伴う地磁気変化は広域に起こっていることがわかります。
図3に、GPS波浪計で捉えた津波を示します。図2で示された全磁力値変化は、地震発生後から大きくなり、津波の沿岸への到達時刻(図3)よりも早いことがわかります。
このことから、各観測点で捉えた全磁力変動は、沿岸に押し寄せた津波による誘導磁場ではないことがわかります。
国土地理院のGPS観測網とNICTの電波観測網による電離圏全電子数(TEC)によると、地震発生後に、TECの波状変化が観測されています(図4)。このことから、地震による地殻変動で変動した海面からの力学的な波が、電離層電流に影響して電離層変動を引き起こし、それが全磁力の変化としてとらえられたと推定されます。
また、1985年以降、日本付近で起きたマグニチュード7.0以上の大地震発生時に、今回と同様な地磁気変化の有無について調べましたが、それらしき地磁気変化は見当たりませんでした。
一方、東北地方太平洋沖地震以降、「いわき」観測点付近では内陸の活断層の活動に伴う地震が多発しています(最大は4月11日のマグニチュード7.0の地震)。これらの地震の震央と「いわき」観測点の距離は、わずかしか離れていないにもかかわらず、「いわき」観測点では、東北地方太平洋沖地震時の様な地震に伴うと思われる地磁気変化は観測されませんでした。

図1 いわき全磁力値と柿岡全磁力値の差分データ
↓で地震発生時刻を示す。時刻は世界標準時
地震発生から15分程度は地磁気が減少し、元の水準に戻るパターンが確認された。
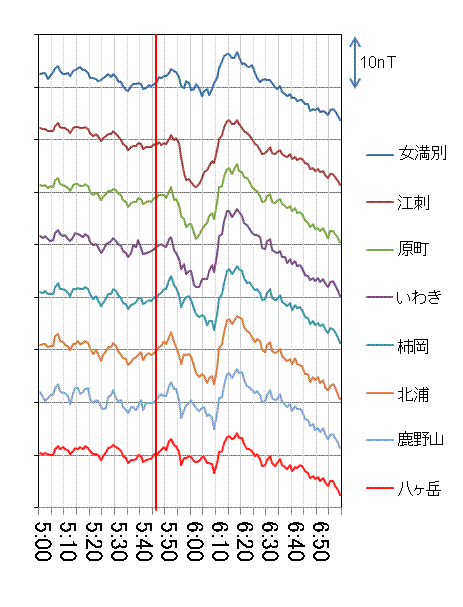
図2 カルマンフィルターを用いた各観測点全磁力値
赤線で地震発生時刻を示す。時刻は世界標準時。
各観測点で地震発生後に地磁気が減少するパターンが確認された。
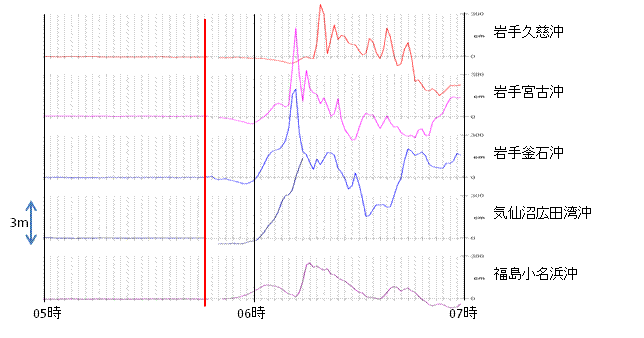
図3 GPS波浪計による海面変動
赤線で地震発生時刻を示す。時刻は世界標準時
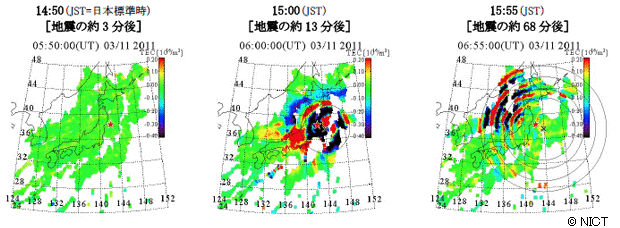
図4 東北地方太平洋沖地震後、高度300km上空に現れた波紋上の波
情報通信研究機構(nict) プレスリリース http://www.nict.go.jp/press/2011/11/111104-02.htmlTEC観測によると、震央から、約170km南東にずれた場所(以下「電離圏震央」)を中心に、 地震の約7分後から波が現れ始め、同心円状に広がっていました。 この電離圏震央は、海底津波計等で推定された津波の最初の隆起ポイントとほぼ一致していました。 赤星は震央、×印は電離圏震央を示しています。同心円の補助線は電離圏震央を中心としています。
